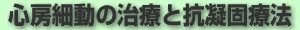
心房細動の治療と抗凝固療法
日本医科大学第一内科教授・日本医科大学付属多摩永山病院内科部長 新 博次
共催 神奈川県保険医協会、第一製薬株式会社
心房細動は、日常診療で頻繁に遭遇する不整脈である。実際に心房細動の症例にどのような対応をすべきかにつき考えると実に多様となる。基本的には、除細動を行うか、心室レートコントロールを行うかといった2つの戦略のうちどちらかが選択される。しかし、実際には除細動を試みたが、うまくいかず心室レートコントロールに方針を変更したり、初期はレートコントロールを考え治療を開始したが、その後の状況により除細動を行う場合もあり、この2つの治療戦略は経過により変更されることも少なくない。最近、洞調律維持と心室コントロールの予後を、総死亡をエンドポイントとして比較したAFFIRM試験と呼ばれる大規模臨床試験の成績が発表され、レートコントロール優位の成績が示された。これは、米国とカナダで施行された多施設無作為割り付け試験で、対象は平均年で70歳、かつ脳卒中ないし死亡のリスクを有し、抗凝固療法の禁忌ではない症例とされた。その結果、総死亡は、有意差はないもののリズムコントロール群で不利な結果であった。脳梗塞の発症はリズムコントロール群ではワルファリンの継続中止により発症したものが多く、結論として、高リスク症例では、洞調律維持がなされていても抗凝固療法を継続すべきとされた。この試験の成績が報告されたため、心房細動を洞調律維持に復帰させることは適切な対応であるが、もはや必須のものではないと見なされることとなった。
過去に、発作性心房細動を発症したヒトは、薬物療法だけでは、たとえ強力な抗不整脈薬を使用しても、その後、心房細動の再発を全くみずして傷害を終えることは現状では困難といわざるを得ない。すなわち、抗不整脈薬を使用した際の心房細動予防効果は決して高くなく、最も効果的と見なされているアミオダロン服用者では高率に副作用のため投与が中断される現実がある。このように、抗不整脈薬の心房細動再発予防には限界があり、長期使用に際しては催不整脈作用や心外副作用の問題も考慮しなくてはならない。そこで、無理に洞調律を維持するのではなく、心室レートコントロールにより心機能を管理し、合併症である血栓塞栓症に対して抗凝固療法を施行することで、そのリスクを低下させることができるならば洞調律維持に固執する必要はないであろうと考えることもできる。しかし、「心拍数コントロールを心がけても不整脈に基づく症状を訴える症例、AFFIRM試験で評価されていない器質的心疾患のない若年者の発作性心房細動」では、治療目標を達成するため、より良い治療薬、治療技術の探索を継続すべきといえる。
一方、心房細動においても非薬物治療の目覚しい進歩をあげなくてはならない。カテーテルを駆使し、心房細動を誘発させる異所性興奮の起源(主に肺静脈)を焼灼する方法、さらに肺静脈と左心房の電気的解離を目指した肺静脈隔離法が施行されるようになった現在では、心房細動への対応も更に多様化したといえる。
リズムかレートかの議論も重要であるが、心房細動の治療において忘れてはいけない問題は、いかにして合併症の血栓塞栓症の発症を防止するかである。心房細動では心房における血流の停滞から血栓形成がなされるため、抗血小板薬ではなくワルファリンを使用した抗凝固療法が推奨される。しかし、ワルファリン療法は、食事や併用薬の影響を強く受けるため凝固能をモニターにしながら使用することになる。また、効き過ぎによる出血性合併症を気遣わねばならず、「出血に対する不安」のため、わが国のみならず世界的に使用頻度が問題とされる。今日では、ワルファリンの必要性は広く認識され、徐々に使用頻度が高まっているが、現状をみると、その充足率はまだ5割に満たない程度と思われる。
次に、不整脈の基質を改善するup-stream治療としてのレニン・アンギオテンシン・アルドステロン系抑制をお薦めしたい。高血圧治療薬として使用頻度が高まっているAT1受容体拮抗薬に心房細動予防効果が既に報告されている。ACE阻害薬においても類似の臨床効果が期待できるが、十分な効果を得るための高用量を使用し難いこともありAT1受容体拮抗薬が勧められるところである。
心房細動の治療は、個々の患者の臨床的背景、担当医の裁量によりなされることになるが、この点については今後も変わりはないと言える。洞調律維持という理想的な戦略が、現状での戦術では十分にその真価が発揮できず、二次選択とすべき戦略に優位性を譲ってしまった現実は誠に残念であり、より効果的、かつ安全性の高い戦術の開発が待たれる |
|
![]()
![]()

![]()
![]()
