|
多剤耐性菌感染リスクが高い市中肺炎が拡大
肺炎入院患者の4割がHCAPとの調査も
市中で発症するが、一般的な市中肺炎よりも多剤耐性菌の感染リスクが高い肺炎の存在が明らかになってきた。これらの肺炎は、米国では、医療ケア関連肺炎(HCAP)と定義され、通常の市中肺炎とは異なる、HCAP独自の治療戦略が必要とされている。日本の研究においても、これらの肺炎患者に対して適切な初期治療を行えなかった場合、死亡リスクが高まることが示されている。
「市中で発症する肺炎の中に、多剤耐性菌の感染リスクが高く、院内肺炎に近いタイプの肺炎が多く存在する」と指摘するのは、名大呼吸器内科の進藤有一郎氏。症例1のように、入院中に発症したものではないが、多剤耐性菌のリスクが高い緑膿菌が検出される肺炎が、かつて市中肺炎と定義されていた患者の中にも存在するという。
現在、肺炎は、病院外で日常生活をしていた人に発症した肺炎(市中肺炎:CAP)と、入院後48時間以降に新たに発生した肺炎(院内肺炎:HAP)の2つに大きく分類されている。CAPとHAPでは、原因菌の抗菌薬耐性リスクが異なるため、異なる初期治療で対処すべきとされている。日本呼吸器学会は、2005年に成人市中肺炎診療ガイドライン(改訂版)を、2008年には成人院内肺炎診療ガイドライン(改訂版)をまとめている。
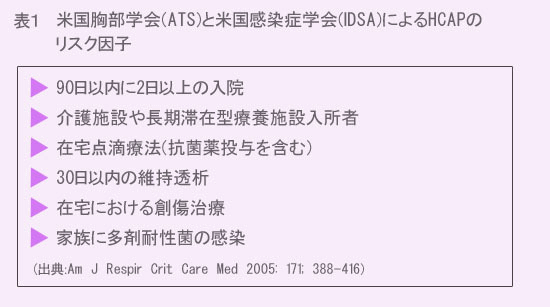
一方、米国胸部学会(ATS)と米国感染症学会(IDSA)は、2005年の合同ガイドライン(ATS/IDSAガイドライン)において、ナーシングホームなどの市中で発症しながらも、CAPよりも多剤耐性菌が原因菌となるリスクが高い肺炎群が存在するとし、新たな肺炎分類として「医療ケア関連肺炎(HCAP)」を提唱している。HCAPは、CAPとHAPの中間に位置するとしている。
HCAPのリスク因子としては、過去90日以内の入院や介護施設の入所者、透析などがあるという(表1)。症例1のようなケースがHCAPの典型例といえる。
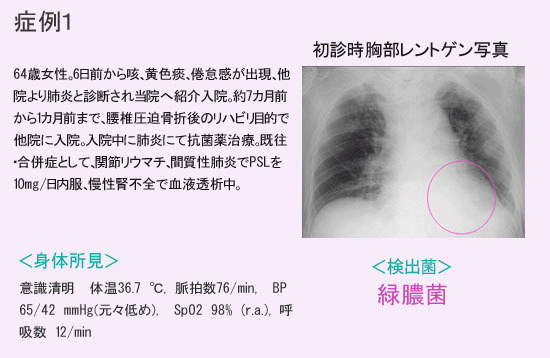
そこで進藤氏は、ATS/IDSAガイドラインを参考に、(1)過去90日以内に2日以上の入院歴がある、(2)介護施設・長期滞在型療養施設入居者、(3)在宅注射患者(外来化学療法・抗菌薬投与含む)、(4)30日以内の維持透析歴(血液透析・腹膜透析含む)がある、(5)在宅での創傷治療を受けている―のいずれかの項目に当てはまる肺炎をHCAP群として、いずれの項目にも当てはまらない一般的な市中肺炎(CAP群)と比較する調査を行った。
前勤務先であった半田市立半田病院(愛知県半田市)で、2005年11月1日から2007年1月31日までに主病名が肺炎で入院した患者371人を後ろ向きに調査。その結果、HCAPは141人(38.0%)、CAPは230人(62.0%)となり、肺炎で入院した患者のうち約4割がHCAPとなることが明らかになった。HCAPとされた患者の中では、介護施設・長期滞在型療養施設入居者が多く86人(61.0%)で、また、過去90日以内に2日以上の入院歴がある患者も55人(39.0%)に上った。
HCAP群とCAP群の患者比較においては、HCAP群では患者の年齢がCAPに比べて有意に高く(P<0.001)、また、中枢神経系疾患を基礎疾患として持つ患者の割合も有意に高かった(P<0.001)。何らかの基礎疾患を抱える高齢患者が罹りやすいと推測された。
加えて、CAP群の検出菌が肺炎球菌などのグラム陽性菌が多かった一方で、HCAP群では、多剤耐性菌のリスクが高いグラム陰性菌の検出率が高かった。
さらに注目すべきは、HCAP群はCAP群に比べて、死亡率が有意に高かったことだ(表2)。
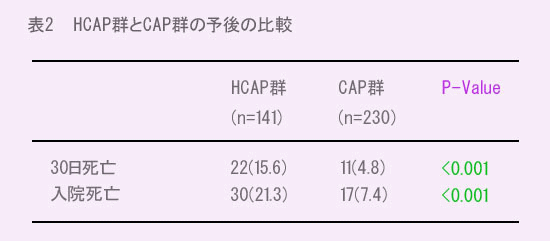
また、治療開始48時間後に症状が改善せず、治療内容の変更が必要になった場合などを初期治療の失敗と定義すると、HCAP群では、初期治療に失敗した際の死亡率が6割に達していた(表3)。
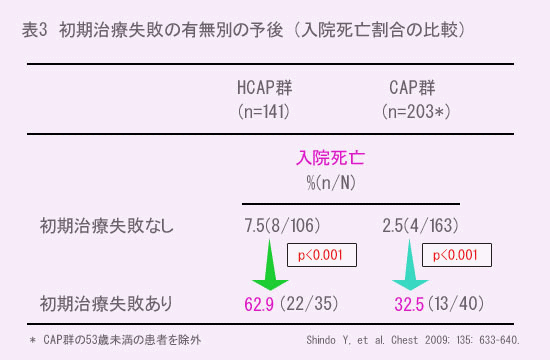
「HCAP群の患者は基礎疾患を有し、体力的な余力がないので、初期治療を失敗すると致命的な経過をたどりやすい」と進藤氏は分析する。「最適な初期治療を行うために、HAPほどではないが、かつてCAPと考えられていた肺炎群の中にも多剤耐性菌リスクが高い肺炎群が存在することを認識すべきではないだろうか」と指摘する。
HCAP全てをHAPと同等に扱うべきか?
では、HCAPの治療はどうあるべきなのだろうか。
「2005年のATS/IDSAガイドラインでは、HCAPすべてを多剤耐性菌のリスクを考慮して治療すべきとされているが、それは過剰だと思う」と進藤氏は語る。HCAPの患者の中から、さらに多剤耐性菌を持つ可能性が高くなるリスク因子を持つ患者を選び出し、治療法を変えるといいのではないかと提案する。
そのリスク因子としては、これまでの研究から、(1)90日以内に2日以上の広域抗菌薬の使用、(2)経管栄養の実施―の2つが指摘できるという。「このリスク因子は、前向き研究で明らかにしていきたい。この耐性菌のリスク因子は、各国・各地域で違いが見られる可能性があり、日本の現状に見合った診療指針を考えるときにはこの点を明らかにしていく必要がある」と進藤氏は言う。
「今までのデータに基づけば、これら2つのリスク因子を持つHCAPに対しては、緑膿菌やMRSAという多剤耐性菌を考慮した広域の抗菌薬を用いた初期治療が必要だろう」と進藤氏は語る。具体的には、成人院内肺炎診療ガイドラインにおけるC(重症)群と同様に扱うといいのではないかとの考え方だ。C群は、多剤耐性菌による感染の恐れがあるため、広域抗菌薬の初期治療が推奨されている。
一方、この2つのリスク因子を持たないHCAPであれば、CAPと同じ治療法でも問題がないとも考え得る。ただし、これらの結果は、あくまで後ろ向きの解析から得られたもの。進藤氏は、「今後、前向きの多施設共同試験で検証する必要がある」と断りを入れる。前向き研究に基づいて、進藤氏の治療戦略で予後を改善することができるか、今後の研究が注目される。
現在、日本呼吸器学会はHCAPのガイドライン作成に着手しており、米国とは大きく異なる日本の医療環境に合うHCAPの定義付けが検討されている。
HCAPの大半は高齢の誤嚥性肺炎
多剤耐性菌感染リスクが高い市中肺炎が拡大
肺炎入院患者の4割がHCAPとの調査も
日本における医療ケア関連肺炎(HCAP)の大半は誤嚥性肺炎となる可能性が示されている。高齢で全身状態が悪く、誤嚥性肺炎を繰り返す患者に対しては、侵襲的な治療を行わない場合も珍しくない。新たなガイドラインが発表されても、高齢でADLの低下した患者に対する治療方針の決め方は、従来と大きく変わらないかもしれない。
「HCAPの患者には誤嚥性肺炎が多く含まれる」。こう語るのは、倉敷中央病院呼吸器内科主任部長の石田直氏だ。
石田氏は、2007年4月〜09年9月に倉敷中央病院に入院し治療を行った肺炎患者のうち、米国胸部学会(ATS)と米国感染症学会(IDSA)によるHCAPについてのリスク因子(表1)のいずれかを満たす患者274人を対象に、誤嚥の有無を解析した。
その結果、対象患者のうち61%が誤嚥性肺炎に分類されたという。また誤嚥群では、原因微生物としてMRSAや嫌気性菌が同定される率が高かった。石田氏は、「誤嚥性肺炎は繰り返しやすく、抗菌薬の投与を繰り返し受けることで、多剤耐性菌のリスクが生じやすい。また、誤嚥性肺炎では口の中の嫌気性菌が起因菌になりやすい」と解説する。
また、死亡率は、誤嚥群では19%と、非誤嚥群の11%よりも高い傾向があった。ただし、この点について石田氏は、「誤嚥を繰り返すような患者は合併症を持つケースが多く、患者側の要因から死亡率が高い可能性がある」と指摘する。誤嚥群では多剤耐性菌の検出率が高いが、多剤耐性菌が死亡の直接的な原因とは断言できないという考えだ。
誤嚥性肺炎の予防のためには、口腔ケアや脳の活性化、原因疾患の治療などが重要だ。しかし石田氏が「寝たきりの患者の肺炎はほとんどが誤嚥性肺炎」というように、ADLが低下した患者において誤嚥性肺炎を完全に予防することは難しい。
実際、石田氏の解析では、誤嚥群は有意に平均年齢が高く(誤嚥群84.2歳、非誤嚥群75.0歳)、パフォーマンス・ステイタス(PS)が悪い患者が多かった。また、誤嚥群では入院日数が非誤嚥群よりも長くなっていた。
患者の状況に合わせて治療内容は個別に検討
米国におけるATS/IDSAガイドラインでは、HCAPのすべてで多剤耐性菌のリスクを考慮して濃厚に治療すべきとされている。
しかし石田氏は、「HCAPに含まれる患者の多くは高齢で、合併症を抱え、PSも悪い。患者・家族が人工呼吸や胃瘻等の侵襲的治療を望まないケースも少なくないため、このような患者に対する治療は画一的に決められない」と打ち明ける。そのため、NHCAPのガイドラインが作成されても、高齢で全身状態が悪く誤嚥を繰り返すような患者に対しては、これまで同様、人工呼吸器などによる管理を選択することは少ないと予想される。
一方、「治療すると決めた患者に対しては、耐性菌のリスクも考慮した上できちん対応すべき」と石田氏。比較的若い患者で、癌など基礎疾患の治療中に肺炎を生じることがあるが、基礎疾患の治療を成功させるためにも肺炎への対応は重要になる。石田氏の調査でも、非誤嚥群に分類された患者は4割に上る。
人生の最期に罹ることの多い肺炎治療においては、いかに死を迎えるかという人の生き方の問題が深くかかわっている。「ガイドラインが公表された後も、患者の状況や患者・家族の意思などによって個別に治療方針を決める基本に変わりはないだろう」と石田氏は語る。
2010.10.4〜6 記事提供:日経メディカルオンライン |
![]()
![]()

![]()
![]()
